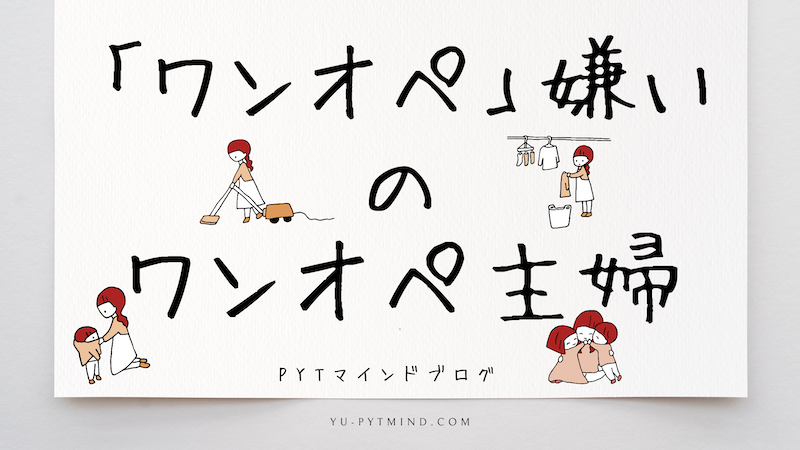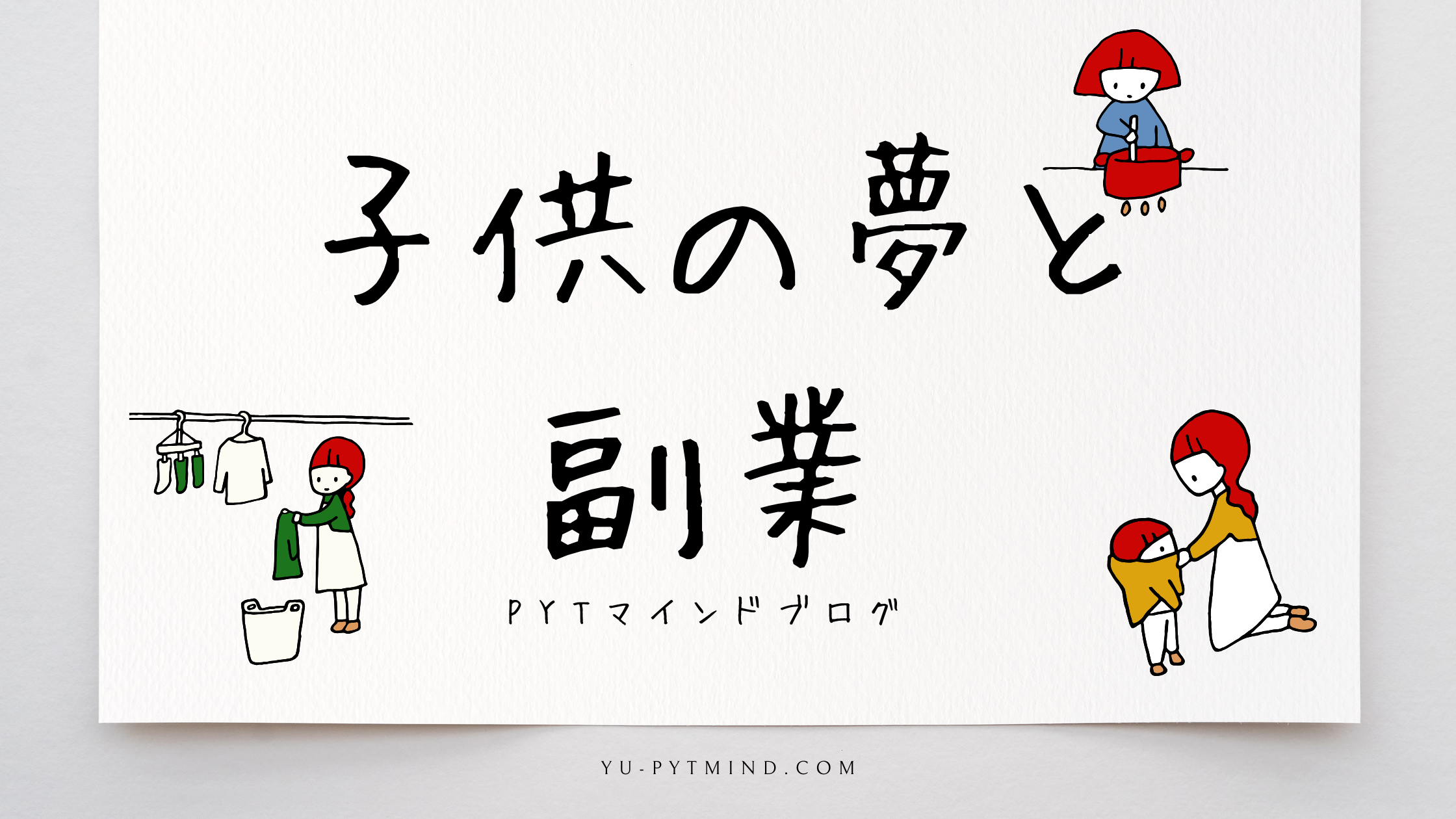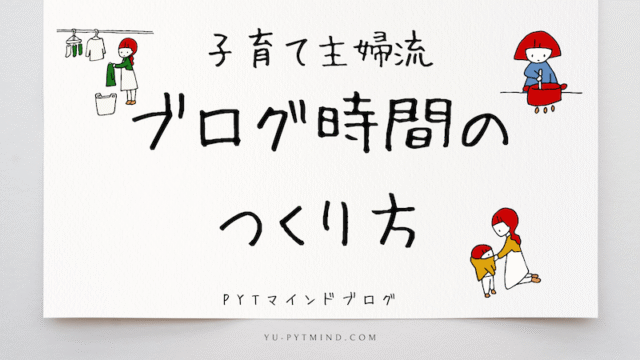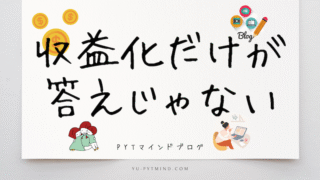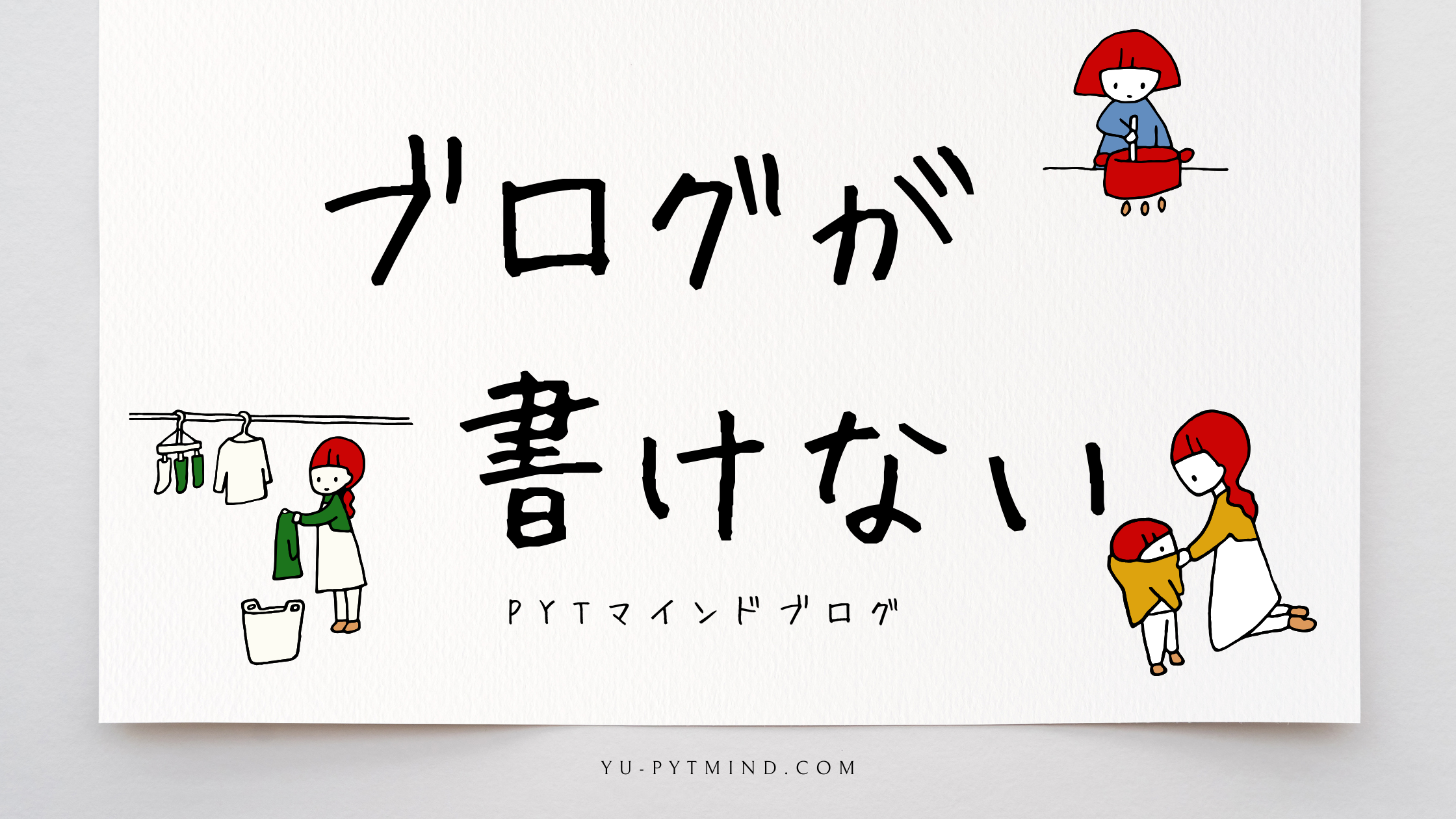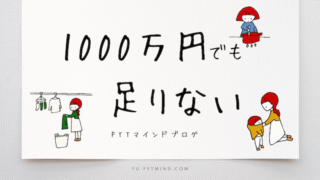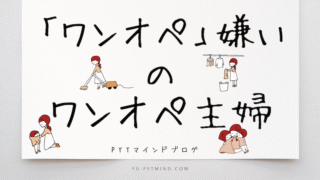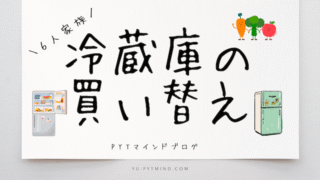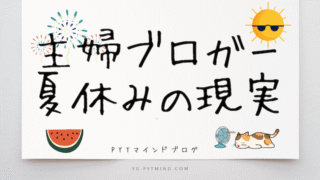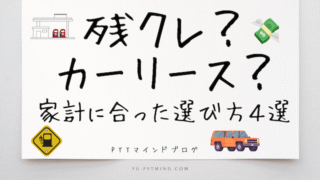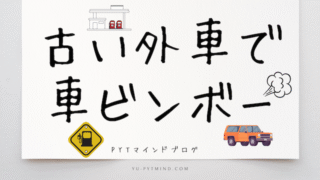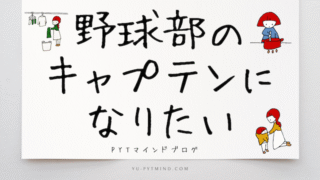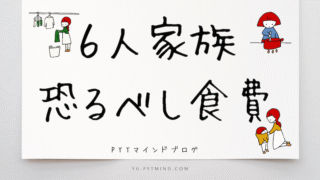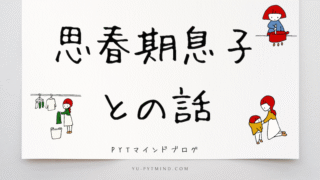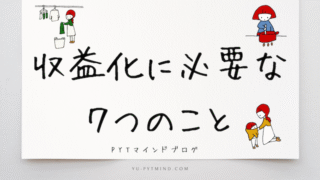“ワンオペ”という言葉、正直私はあまり好きではありませんでした。
『一人で全部やってます!頑張ってます!』とアピールしているように聞こえてしまって、なんとなく距離を置いていたんです。
でも振り返ってみれば、私自身、14年間いわゆるワンオペで子育てをしてきました。
当時はそれを“特別なこと”とも“大変なこと”とも思わず、ただ必死に日々を回していただけ。
そして今になって、“ワンオペ”という言葉の本当の意味をようやく理解するようになりました。
本来は飲食業界の言葉で、店員がひとりで接客から調理、片付けまでを担う“ワンオペレーション”が由来です。
深夜の牛丼チェーンで、店員ひとりにすべてを任せる「ワンオペ問題」が社会問題になり、そこから『ワンオペ育児』という形で子育ての場面にも広まっていきました。
14年間のワンオペ育児

長男が生まれてから14年。
最初の3年間は夫が単身赴任で、完全にひとり。
その後も転勤族になり、実家や友達は遠く、頼れる人はいない。
子どものオムツ替えやごはんの準備、着替え、寝かしつけももちろん、幼稚園や学校行事。
家事全般も私の担当です。
夫は朝から晩まで仕事で忙しく、時間がある時にお風呂に入れてくれるくらいで、家のことはほとんど何もしない。
でも当時はそれを“大変”と思うことはあまりなく、「これが普通」だと思っていました。
きっとそれは私の父もそういうタイプだったから。
遊ぶ時は全力で遊んでくれる、愛情も注いでくれる。でもお世話や家の事をしてくれたのは”母”。そんな印象です。
『男は外で働き、女は家を守る』――そんな古い価値観を自然と受け入れていたんだと思います。
「すごいね」と言われても…
4人育児をしていると、よく言われます。
「え、4人も!?すごいね!」
「尊敬する!〇人でも大変なのに…」
もちろんありがたい言葉なんだけど、当事者としてはちょっと違って。“すごい”というより、“やるしかなかった”が本音です。
…実際のところ、『すごい』以外にかける言葉ってあんまりないんだろうなとも思います(笑)
必死で日々を回しているだけで、特別なことをしている意識なんて全然ない。上手く出来ないことばかりで「頑張れてる!」なんて自信は1ミリもありません。
それはきっと子どもが1人でも2人でも同じで、「人数が多いから大変」「少ないから楽」という単純なものじゃないんだと思います。
結局、「4人いるだけで頑張ってる」なんてことは全然ありません。
だからこそ『ワンオペです』という言葉を目にしても、あまり特別感を感じず、「みんなそんなもんじゃないの?私も同じだけどな…」と感じていました。
気づいた瞬間
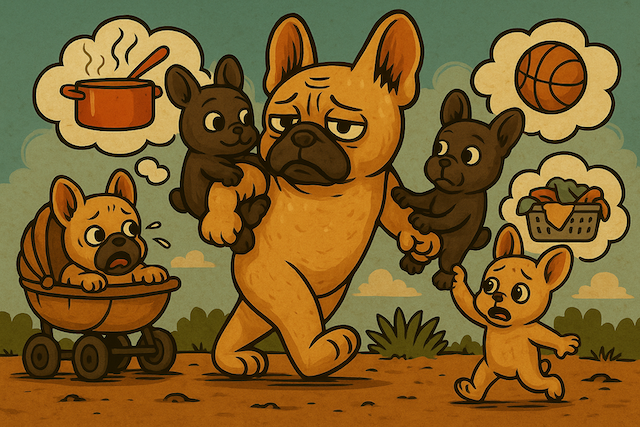 でも今になって振り返ると『私、頑張ってきたんだな』と思う瞬間があります。
でも今になって振り返ると『私、頑張ってきたんだな』と思う瞬間があります。
- 夜泣きで一晩中抱っこしながら、ウトウト朝を迎えた日。
- なんで泣いてるのか分からなくって、子どもと一緒に泣いた日。
- 外で駄々を捏ねて動けなくなったり。
- 家事が溜まっていても、「公園へ行きたい」を叶えてあげるために必死だった。
- おんぶに抱っこでベビーカーを引いてのスーパーも。病院も。
毎朝の送り出しまでの大変さもそうだ。(現在進行形)
「あぁ、私、全部ひとりで背負ってきたんだな」
って。
当時は必死すぎて“大変さ”を意識する余裕もなく、「これが普通」だと思って走り抜けてきました。
でも子どもたちが成長して、ほんの少し余裕が生まれた今だからこそ、ようやく自分の頑張りやしんどさを振り返れるようになったんだと思います。
一緒に育児するということ
そして気づきました。
一緒にやってこなかった代償は普段の夫との会話の中で徐々に生まれてくるんです。
こんなことあったよね、あの時こうだったよねの会話にズレがあったり、子育ての大変さを理解していない発言が出たり。
「もう一人欲しいなー」なんて軽いノリで言われた時にはもぅ…笑えない。
そんな体験から思ったんです。
子どもの可愛さは共有できても、大変さは体験しなきゃ絶対に伝わらない。
一人で抱え込むと、知らないうちに心に積もっていってしまうんです。
大変さや苦悩を体感して分かち合うことが、本当の「一緒に子育てする」ということなんだなと今は思います。
私は「やらなくていいよ」と言ってきたし、「手伝って」と言えなかったのも自分。
だからこそ余計に感じるんです。
ーーもっと一緒に育児してこられたらよかったな、と。
ワンオペの末路
私が14年間ワンオペで育児してきて、今になって感じることがあります。
「末路」なんてちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、これは決して脅しじゃなくて、実際に”積み重ねから生まれた”我が家の現実です。
-
子どもとの関係に差がつく
誰が寄り添ってくれたのか、どちらが頼れる存在なのか――子どもはしっかり感じています。その積み重ねが親子関係の形を作り、一緒に“やってきたかどうか”は距離感に確実に現れます。ごまかしも取り繕いもできません。 -
夫婦関係に積もる
「しんどいときにやってくれなかった」という感情は、忘れたつもりでも積み重なって残っていきます。大変なこと、しんどいことを共有してこそ、絆は深まる。それは夫婦間でも同じです。 -
パパ自身の後悔が生まれる
子どもはいずれ必ず親から離れていきます。悲しいけれど、特に父親からはその時期が早く訪れることもあります。「もっと関わればよかった」と後悔してからでは遅いのです。
でも我が家も、まだ諦めてはいません。
私の日々のチクチクの甲斐もあってか、少しずつではあるけれど、夫にも変化が見えます。
「送迎行くよ」と声をかけてくれたり、休日に子どもと過ごす時間が増えてきたり。
大きなことじゃなくても、こうした小さな一歩がこれから先の関係を変えていくんだと思います。
子育ては続いているし、夫婦の時間もまだまだこれから。
「もう遅い」なんてことはないからこそ、我が家も一緒に歩み直していきたいと思っています。
「共感し合える」言葉
結局「ワンオペ」って、育児の大変さや、しんどいと言えないもどかしさ、苦労…そういうものを、たった一言で表せる言葉なんだと思います。
けしてそれはアピールではなくって、その言葉があるからこそ、同じ経験をしているママたちと共感し合える。
ママにとっては、実はすごく便利な言葉なんですよね。
もし今、子育ての真っ最中で「私もしんどい」と思っている人がいたら――
それは決して弱音じゃないし、当たり前の感情です。
SNSが普及している今だからこそ、繋がって助け合える環境もある。上手にそれを活用できたらいいなと思います。
そして、育児は誰かと一緒にやることで、ずっと豊かになります。
近い未来のために
ワンオペはママだけでなく、子どもにもしわ寄せがいくものです。
特に兄弟がいると、お兄ちゃんやお姉ちゃんが我慢を強いられることもあります。
だからこそ、子どもたちのためにも“誰かに頼ること”を忘れないでほしい。
そしてもしこれを読んでいるパパさんがいたら。
「ママに任せっぱなし」になっていないか、少し立ち止まって考えてみてほしいです。
子どもの可愛さは共有できても、大変さを一緒に経験しなければ、ママの信頼は得られない。そして、その空気を読んだ子どもも自然と“ママ、ママ星人”になってしまいます。
その差は年月を経て、夫婦関係や親子関係に確実に残ります。
後になって「もっと一緒に関わればよかった」と後悔しないように――
今からでも遅くはない。ほんの少しでも“分かち合う”一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいなと思います。